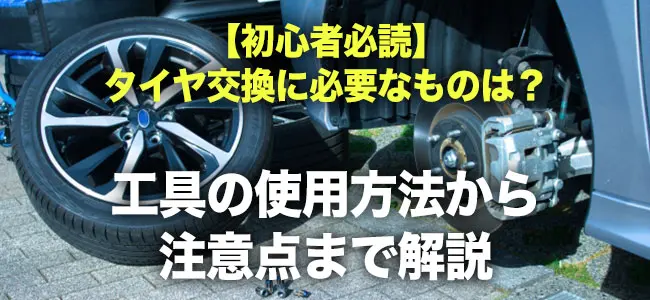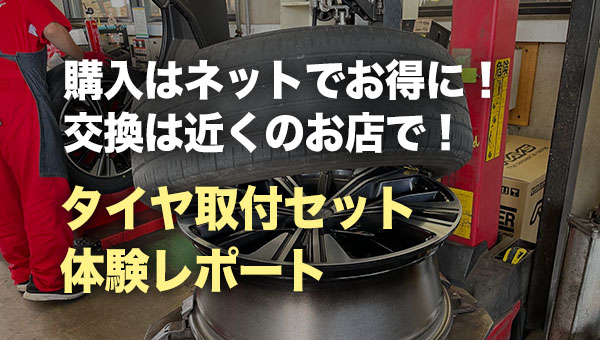「ピンチカットって何?」
「タイヤにコブができたけど小さいから大丈夫だよね?」
タイヤに小さなコブができたとき、このまま走行できるか不安になりませんか?タイヤにできたコブは危険な見た目をしているので、どうしたらいいかわかりませんよね。
結論、コブが発生したタイヤは大小にかかわらず早急に交換しましょう。
ピンチカットとは、タイヤの側面にできるぽっこりとしたコブのような膨らみのこと。小さいピンチカットだと気にしなくていいと思われがちですが、大きさは関係ありません。ピンチカットが発生した場合、すぐに対処しないと事故につながる可能性があります。
そこで当記事では、ピンチカットの原因や放置する危険性を紹介します。ピンチカットをできる限り発生させないようにし、走行中のトラブルを未然に防止しましょう。
- タイヤのピンチカットとは側面のコブのこと
- タイヤのピンチカットの原因
- 大丈夫?ピンチカットを放置する危険性やリスク
- タイヤのピンチカットを予防する方法
- タイヤにピンチカットができたときの対処法
- ピンチカットしたタイヤの交換はベストにおまかせ
- タイヤのピンチカットは危険|即交換しよう
タイヤのピンチカットとは側面のコブのこと

ピンチカットとは、タイヤの側面にできるコブのことです。タイヤ内部のカーカスコードが切れ、空気が保持できなくなったときにピンチカットが発生します。
カーカスコード<とは、タイヤ全体を支えるポリエステルやナイロン、レーヨンを編んだものです。

カーカスコードはタイヤの空気を保持したり車の荷重を支えたりと、重要な役割を果たしています。また、タイヤのトレッド面にはベルトと呼ばれる金属の補強板がありますが、サイドウォールは表面のゴムの下がカーカスコードです。
そのため、サイドウォールはカーカスコードが切れやすく、タイヤ内部の空気が保持できずにコブができてしまいます。ピンチカットができている状態はタイヤを支えているカーカスコードに異常があるため、極めて危険な状態だといえるでしょう。
タイヤのピンチカットの原因

タイヤにピンチカットができる原因は、以下の4つが挙げられます。
● 空気圧の低下
● 過積載
● タイヤの劣化・不良
ピンチカットが起きる原因を理解し、事前に対策を取りましょう。
縁石との接触
走行中にサイドウォールを縁石にぶつけてしまうと、ピンチカットが発生することがあります。サイドウォールはトレッド面に比べて耐久性が低いため、衝撃で損傷してしまいます。
ピンチカットが発生する状況は、主に以下の通りです。
● 右折待ちの車を避けるため左に寄せたらタイヤを縁石にこすった
上記のように速度を出していないような状況でも、ピンチカットは発生します。そのため車のボディだけでなく、タイヤの側面にも気を配り、運転するのがおすすめです。
空気圧の低下
タイヤの空気圧が低下していると、サイドウォールに負荷がかかるためピンチカットが発生しやすくなるでしょう。
サイドウォールは空気圧が低いと、荷重を受けている部分が横に膨らむため、常に負荷がかかっている状態になります。やがて、タイヤ内部のカーカスコードが切れてしまい、ピンチカットが発生します。
空気圧はピンチカットだけでなく、燃費やタイヤの寿命にも影響する重要な項目です。そのため、異常がなくても定期的に点検しましょう。空気圧の点検は、ガソリンスタンドやカー用品店で無料でできるため、給油のついでに一声かければチェックしてくれます。
過積載
車に荷物を積んだままにしているのも、ピンチカット発生の原因になります。荷物を多く載せていると車重が重くなり、荷重を支えているカーカスコードに負荷がかかるためです。
たとえば、キャンプが趣味の方は荷物を降ろすのが面倒で、積んだままにすることがありませんか?また、収納場所がないからといって、車の荷室を収納がわりにしているかもしれません。家族分キャンプ道具があると重量も増え、さらにタイヤへの負担は増えるでしょう。
ピンチカットを防ぐためにも、キャンプから帰宅したら車から荷物を降ろし、できる限りタイヤの負荷を減らすのがおすすめです。
タイヤの劣化・不良
ピンチカットは、購入したばかりのタイヤにも発生する可能性があります。これは、購入したタイヤの品質が悪い場合に起こります。
自分自身でタイヤ側面をぶつけていないのにピンチカットが発生した場合は、購入店に持ち込んでみましょう。初期不良が認められれば、交換してくれることがあります。
また、寿命が近づき劣化しているタイヤは、ピンチカットが発生しやすい状況です。タイヤの寿命は3〜5年なので、定期的に交換してトラブルを未然に防ぎましょう。
関連記事:夏タイヤの寿命はどれくらい?長く使い続けるコツを5つ紹介
大丈夫?ピンチカットを放置する危険性やリスク

ピンチカットを放置する危険性やリスクを紹介します。
● 車検に通らない可能性がある
ピンチカットが小さくても、放置しておくのは危険です。コブが小さいから大丈夫だと思わず、ピンチカットの危険性を理解しておきましょう。
いつバーストしてもおかしくない
ピンチカットが発生したからといって、すぐに走れなくなるわけではありません。しかし、側面のカーカスコードが破損しているため、いつバーストしてもおかしくない状況です。
ピンチカットが発生したタイヤは、車の荷重や走行中の振動により内部のゴムが剥がれ落ちていきます。そのため、見た目は変わらなくてもタイヤ内部から劣化が進み、ある日突然バーストしてしまうでしょう。
ピンチカットが発生したタイヤは、内部から劣化していきます。最悪の場合、重大な事故につながる恐れもあるため、ピンチカットが発生したタイヤはできる限り早く交換しましょう。
関連記事:【危険】車のタイヤがパンクした状態で走行する危険性と対処方法を解説
車検に通らない可能性がある
タイヤにピンチカットが発生していると車検に通りません。車検の項目には「タイヤの摩耗・損傷」に関する項目があり、道路運送車両法にも明記されています。
亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
ピンチカットはタイヤ内部のカーカスコードが破損している状態なので、車検には通りません。他にも車検に通らないタイヤの例として、スリップサインが見えているタイヤが挙げられます。
車検前にはタイヤにスリップサインは出ていないか、損傷はないか、などの点検をしておきましょう。
関連記事:【危険?】車検に通らないタイヤの特徴5選!車検に通るタイヤの管理方法も解説
タイヤのピンチカットを予防する方法

ピンチカットの発生を予防する方法を紹介します。「ピンチカットを発生させたくない」と感じた方は、参考にしてみてください。
- 安全運転を心がける
- 月に一回の空気圧点検
- アウトドア時でも過積載しない
ピンチカットを未然に防げば、旅行やキャンプなどレジャーを楽しんでいる最中の思わぬトラブルも防止できます。
1.安全運転を心がける
タイヤの側面にダメージを与えるような運転はしないようにしましょう。
● 急ブレーキ
● 急カーブ
● 急発進
上記4つの運転をすると、タイヤが一時的に変形し、側面に負担がかかります。また、ピンチカットだけでなく、タイヤの摩耗スピードや寿命にも影響します。
タイヤに負荷をかけない運転は、具体的に以下のようにするのがおすすめです。
● カーブ前には減速する
● 発進時はゆっくりアクセルを踏み込む
他にも挙げればキリがありませんが、安全に落ち着いてゆとりのある運転をするといいでしょう。安全運転は事故の防止だけでなく、車自体にとってもプラスになります。
2.月に一回の空気圧点検
空気圧の点検を定期的にすることで、ピンチカットの発生を予防できます。空気圧が低下すると、タイヤの側面がたわみ負荷がかかるため、空気圧を適正に保つのは重要です。
タイヤの空気圧点検は、ガソリンスタンドやカー用品店で無料で点検できます。ガソリンスタンドは給油のついでに頼めば点検してくれるので、手間がかからずおすすめです。
また、空気圧の点検はタイヤが冷えた状態で行いましょう。高速走行したあとはタイヤ内部の空気があたたまり、熱膨張によって空気圧が上昇しているため、正確に測定できません。
月に一回、自宅の最寄りのガソリンスタンドで点検してもらえば、ピンチカットの発生を予防できます。
3.アウトドア時でも過積載をしない
アウトドアは過積載になりやすく、タイヤに負荷がかかります。とくにキャンプは荷物が増えやすいため、家族だと車の荷室がパンパンになる場合もあるでしょう。さらにルーフキャリアを利用し、屋根にも荷物を積んでいるとかなりの重量になっていると予想できます。
タイヤに負荷がかかるとピンチカット発生の原因になるため、なるべく荷物を減らしましょう。また、軽量でコンパクトなキャンプ道具を利用すれば、重量を減らせるので過積載の防止になります。
アウトドアの荷物を必要最低限に抑えられれば、ピンチカットの予防につながるでしょう。
タイヤにピンチカットができたときの対処法
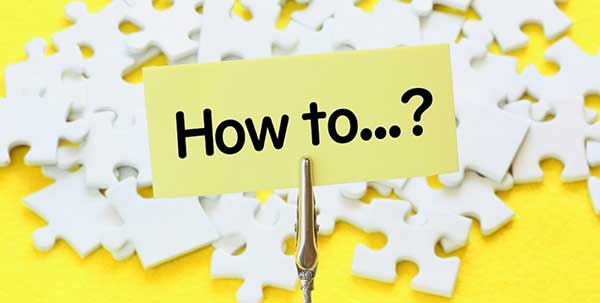
予防策を実践していたのにもかかわらず、ピンチカットができてしまったときの対処法を紹介します。
- 早急にタイヤ交換
- レッカーを呼ぶ
- 運転を控える
ピンチカットが発生した場合、応急処置はありません。ピンチカットの対処法を知っておき、いざというときに対応できるようにしましょう。
早急にタイヤ交換
ピンチカットが発生したタイヤは修理ができないため、すぐに交換するのがおすすめです。
理想は4本交換ですが、タイヤを交換したばかりの場合は1本だけの交換でも問題ありません。また、2本を新品に交換し、ローテーションして利用する方法もあります。
ピンチカットが発生したタイヤは、遅かれ早かれ必ず交換が必要です。すぐにタイヤを交換し、危険な状態で走行しないようにしましょう。
関連記事:タイヤがパンク!1本だけ変える?4本変えた方がいい?そのお悩み解決します!
レッカーを呼ぶ
走行中にピンチカットを発見し、運転するのが怖いと感じた場合はレッカーを呼びましょう。レッカーは、任意保険にロードサービスとして付帯していることがあるので、一度加入している保険内容を確認してみてください。
近くにタイヤ交換できるお店があるときは、ハザードを出して左に寄りながらゆっくり走行して向かうと安全です。
ピンチカットの大きさ次第では、運転するのが怖いと感じることもあると思います。決して無理をせず、レッカーを呼んで大きな事故にならないようにしましょう。
運転を控える
自宅でピンチカットを発見した場合は、運転を控えましょう。できる限り、自宅に近いガソリンスタンドやカー用品店を選び、早急にタイヤを交換するのがおすすめです。
自宅近くにタイヤ取付店が見当たらない方は、ベストの提携店舗も探してみてください。自宅近くのタイヤ交換店を見つけられるかもしれません。
ピンチカットが発生したタイヤで運転するのが怖い方は、レッカーを呼びましょう。
ピンチカットしたタイヤの交換はベストにお任せ

ピンチカットが発生したタイヤの交換はタイヤワールド館ベストにお任せください。全国に約4,000の提携店舗があるため、最寄りのタイヤ交換店が見つかるかもしれません。
ベストの提携店舗では、オンラインショップで購入したタイヤを直送し、来店するだけでタイヤを交換が可能です。タイヤはオンラインで購入するほうが安い傾向にあるのですが、通常、持ち込みタイヤの工賃は高くなります。
しかし、ベストのタイヤ交換は、オンラインでタイヤを購入しても工賃が上がらないので、オンラインと実店舗のメリットを兼ね備えたサービスといえます。オンラインでタイヤの購入から取付日の予約まで完結できるので、忙しく時間がない方にもおすすめです。
タイヤのピンチカットは危険|即交換しよう

タイヤのピンチカットは内部のカーカスコードが切れ、とても危険な状態です。そのまま乗り続けるといつバーストするかわからないので、ピンチカットが発生したタイヤはできる限り早く交換しましょう。
また、タイヤのサイドウォールは弱いため、縁石にこすったり空気圧が低い状態が続いたりすると負荷がかかり、ピンチカットが発生します。
ピンチカットの発生を防ぐためには、月に一回の空気圧点検や安全運転を心がけるのが重要です。


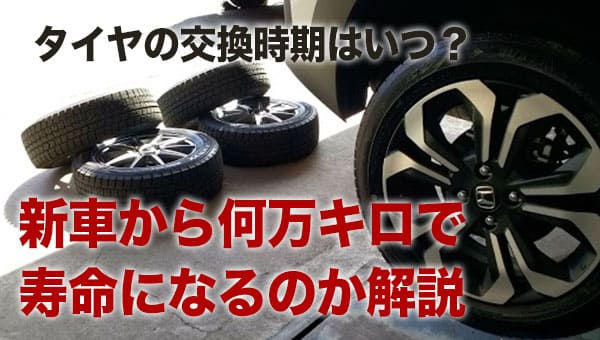

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!
タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、
購入する時のポイントなど
足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!
公式InstagramやTwitterも更新しているので是非
そちらもご覧ください!









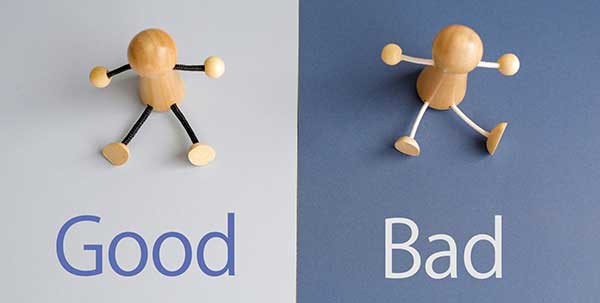


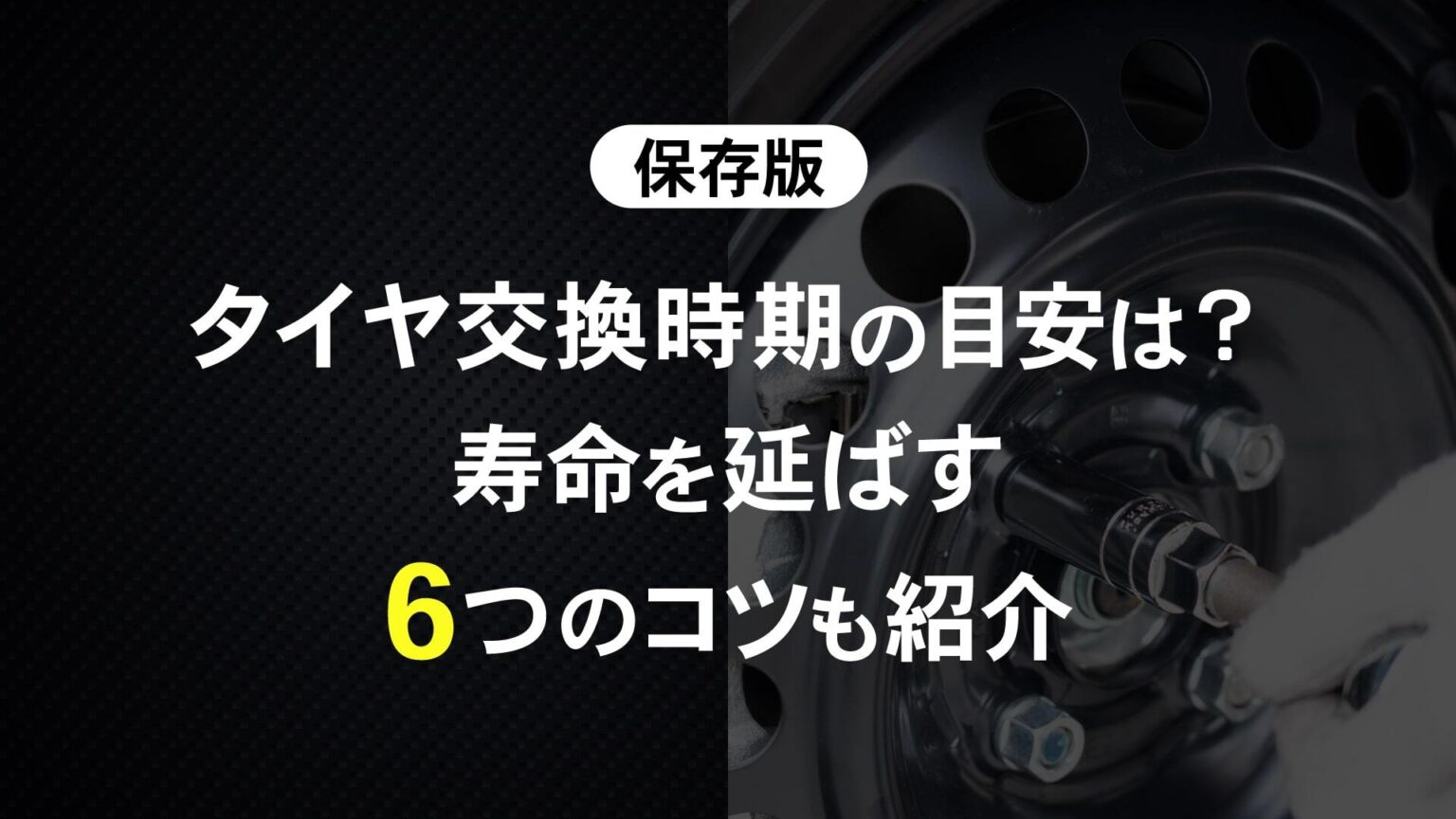





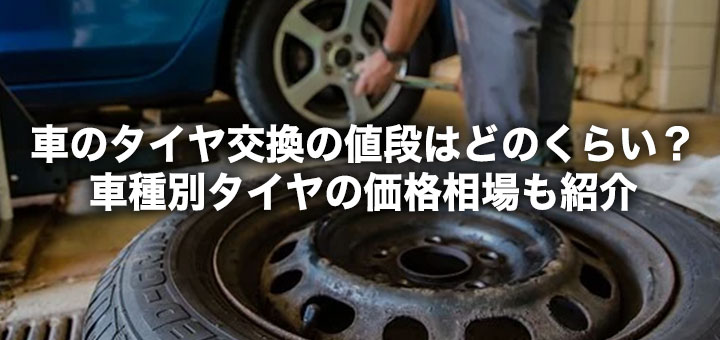
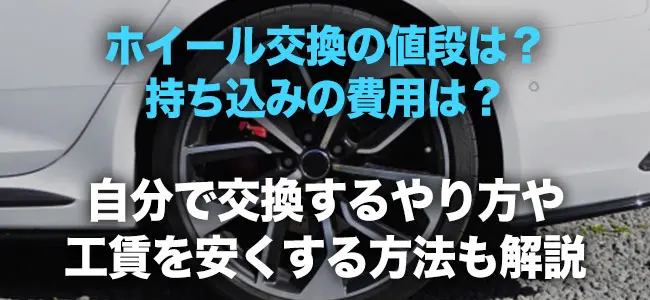













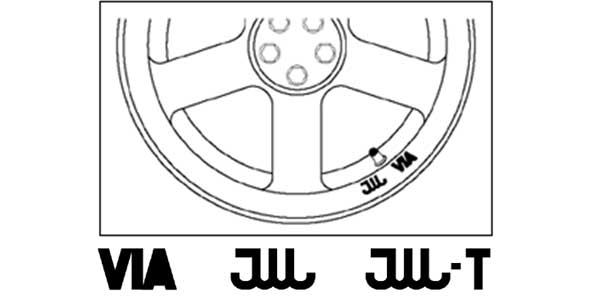


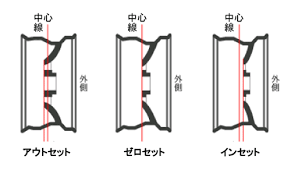


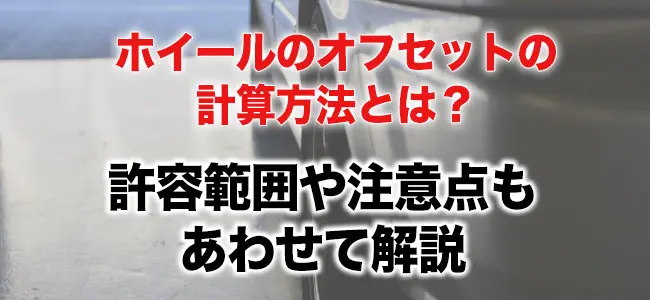


















































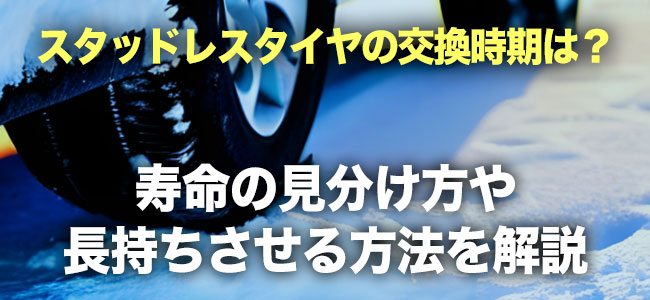
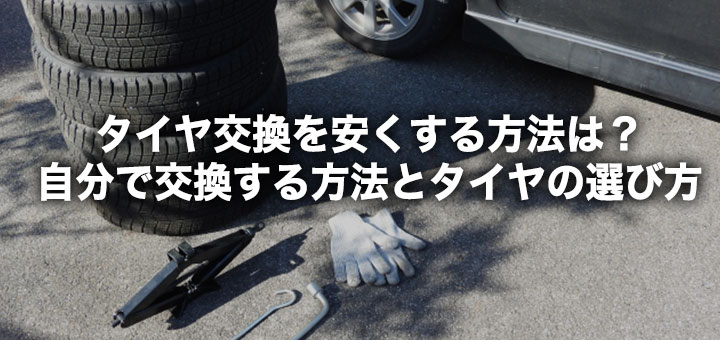











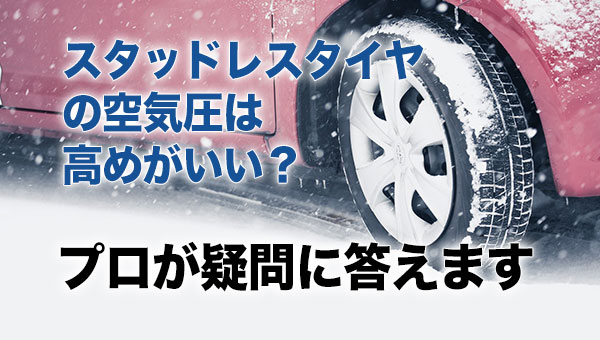

















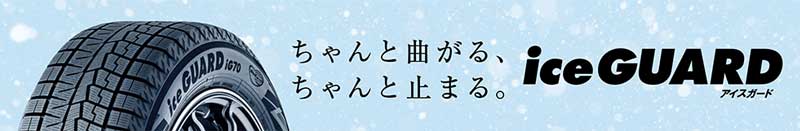




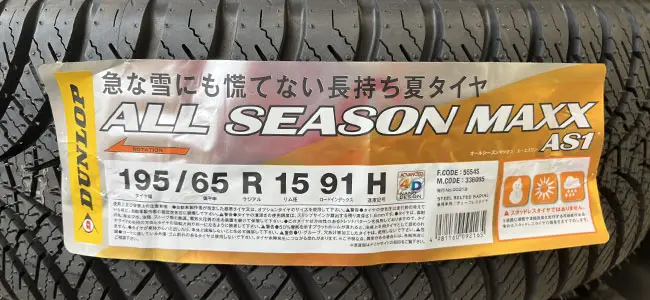















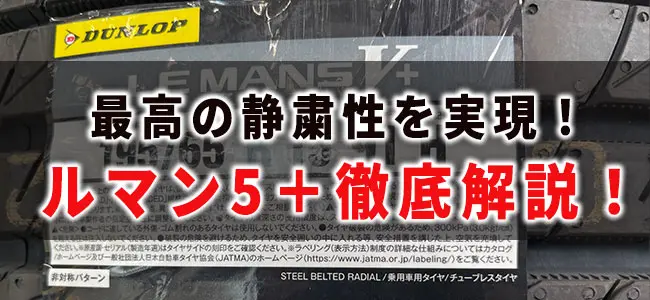




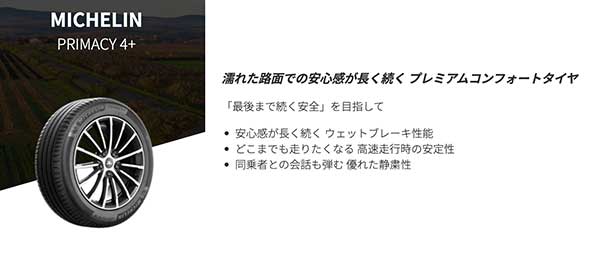






 静かなタイヤはタイヤワールド館ベストにおまかせ” class=”headline-img”>
静かなタイヤはタイヤワールド館ベストにおまかせ” class=”headline-img”>