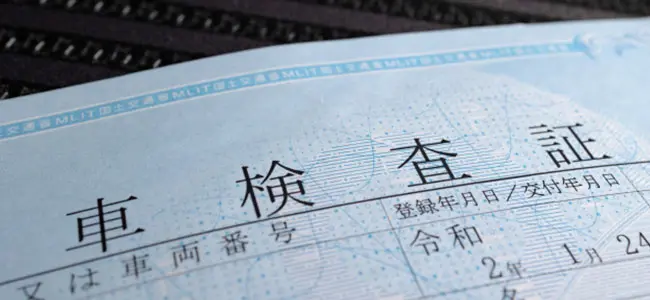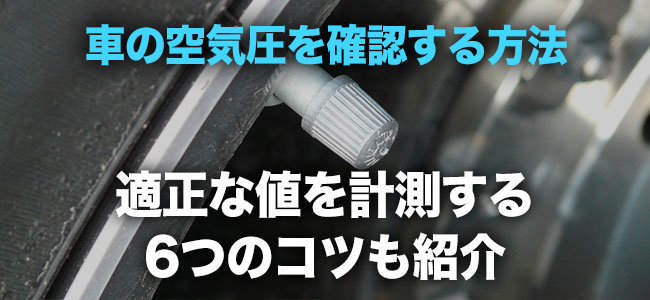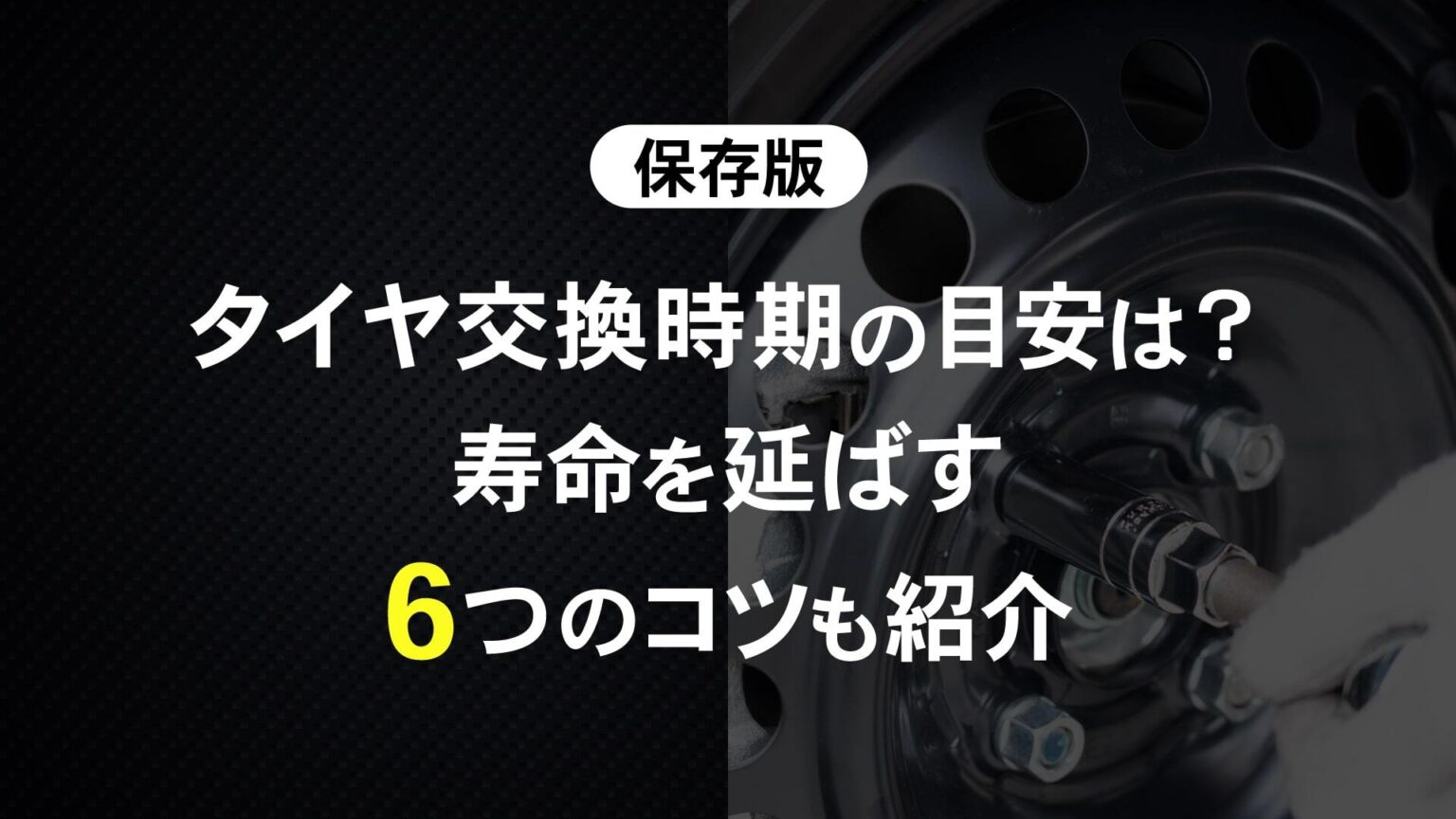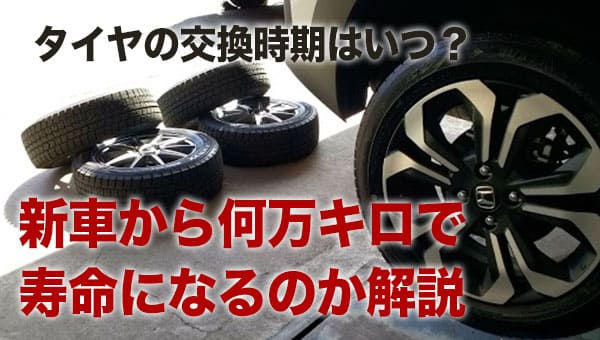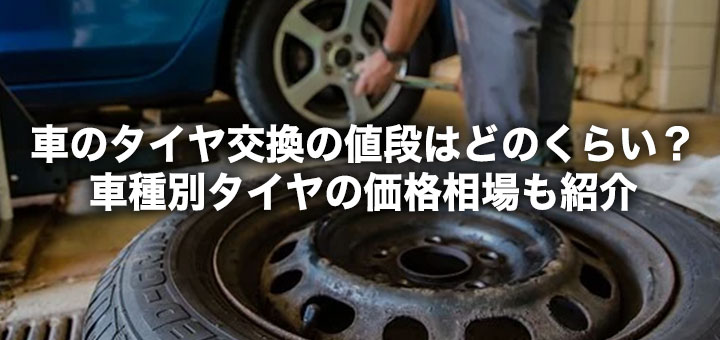最終更新日 2025年3月21日
車を利用しているなら、車検を避けては通れません。車検ではさまざまな点から車の状態をチェックされますが、タイヤの溝の深さも点検項目のひとつです。
しかし、どれくらいの溝の深さであれば車検に合格するのか知っている方は少ないのではないでしょうか?
本記事では車検に合格するタイヤ溝の深さや、初心者でもできる車検前のタイヤ溝の測り方、タイヤを長持ちさせる方法などについて解説します。
- 車検にてタイヤの溝が測られる理由
- タイヤ溝の深さの合格基準
- 初心者でもできる車検前のタイヤ溝の測り方
- 溝の深さ以外に車検に落ちやすいタイヤの特徴
- タイヤを長持ちさせる方法
また、溝が減ったタイヤを使い続けるリスクや車検費用を抑えるポイントも紹介しています。タイヤの安全性や、車検の費用負担などを気にしている方にも役立つ内容です。
本記事を参考に、車検に向けてタイヤ溝の合格基準や測り方を事前に知り、対策を講じられるようにしておきましょう。
- 5円玉を使ったタイヤの溝の測り方
- スリップサインが出たタイヤを使い続ける3つのリスク
- ┗1.走行性能に支障が出る
- ┗2.ハイドロプレーニング現象が発生しやすくなる
- ┗3.パンクやバーストの恐れが高まる
- 溝以外も確認!車検に落ちやすいタイヤの特徴
- ┗ひび割れや傷
- ┗タイヤの変形
- ┗空気圧の低下
- 車検費用を安く抑える3つのポイント
- ┗1.ユーザー車検を利用する
- ┗2.複数の業者に見積もりを依頼する
- ┗3.必要最低限の項目だけ検査してもらう
- タイヤを長持ちさせるための5つの対策方法
- ┗1.ローテーションで摩擦を軽減する
- ┗2.適度に空気圧を調整する
- ┗3.急発進や急停止を控える
- ┗4.タイヤを適切な場所に保管する
- ┗5.ホイールアライメントを調整する
- タイヤの溝に関するよくある質問
- ┗タイヤの溝が4mmだと車検に通らない?
- ┗タイヤの寿命はどのくらい?
- ┗タイヤは1本だけ溝が少なくても4本交換したほうがいい?
- タイヤの点検ならタイヤワールド館ベストがおすすめ
5円玉を使ったタイヤの溝の測り方
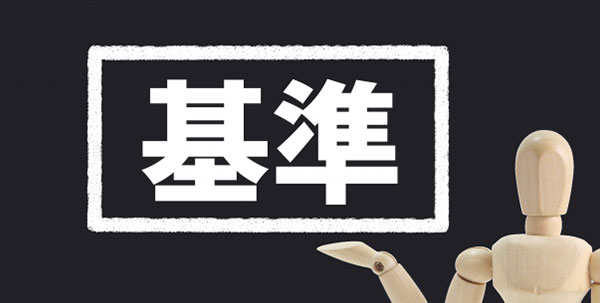
車検ではタイヤ溝の深さの合格基準は、乗用車・軽トラック以上であれば1.6mm以上と明確に決まっており、高速道路においては車種によってサイズは異なります。
以下は車種・道路による合格基準の早見表になります。
| 車種 | 一般道路 | 高速道路 |
| 乗用車・軽トラック | 1.6mm | 1.6mm |
| 小型トラック | 1.6mm | 2.4mm |
| 大型トラック・バス | 1.6mm | 3.2m |
高速道路では一般道路に比べ、スピードが速いので大きな事故が起こりやすいことから、溝の深さが一般道路に比べ深くなっています。
車検でタイヤの溝の深さが測られる3つの理由

タイヤは車が走行する上で重要な役割を担っており、タイヤの状態は車検において厳しく確認される項目のひとつです。
タイヤ溝には保安基準が設けられており、基準に満たない場合は不合格となります。
車検では運転の安全性を考慮してタイヤ溝が測られるので、事前に溝の深さを確認することが重要です。
また、燃費や環境面などへの影響にも配慮されているため、車にかかる費用の節約や環境保全の効果も期待できます。
1.運転する際の安全性が考慮されている
運転の安全性を考慮するのが、車検の際にタイヤ溝の状態を確認される理由の1つです。タイヤは消耗品なので、運転に伴って摩擦して徐々にすり減ったり、劣化していったりします。
タイヤに傷が蓄積されていくと、ブレーキ機能やハンドリング機能が低下し、安全に運転できなくなります。
とくに、路面が濡れている場面ではタイヤ溝が浅くなっていると、路面とタイヤの間に水の膜ができる「ハイドロプレーニング現象」が起こり、ハンドルが取られて車体がスリップしてしまうため注意が必要です。
運転する際の安全性を考慮して、タイヤは定期的に交換することが望ましいでしょう。
2.道路運送車両法で罰則が規定されている
タイヤの溝の深さは運転の安全性に大きく関係していることから、国土交通省で保安基準が設もうけられており、基準に満たない場合は公道を運転できません。
基準値未満にもかかわらず、公道を運転していた場合は道路交通法違反となり、「違反点数2点の加算」 、普通自動車の場合は「9,000円の罰金」(2025年2月時点)が科されます。
気付かずに運転していることもありますが、安全面や法律面における罰則もあるので、定期的にチェックするようにし、溝が浅い場合は交換するようにしましょう。
3.燃費や環境面などへの影響に配慮されている
タイヤの溝の深さは、車の燃費や環境への影響にも関係しています。溝が浅くなるとタイヤの転がり抵抗が大きくなり、スムーズに進みにくくなるため、余計なエネルギーが必要です。
転がり抵抗が大きくなると燃費が悪くなり、ガソリンを多く消費することになります。ガソリンを使う量が増えると、二酸化炭素(CO₂)の排出量が増え、地球温暖化の原因となるでしょう。
さらに、タイヤが摩耗するとゴムの微粒子が削れて空気中や道路に広がり、環境汚染の一因となる可能性があります。
そのため、車検ではタイヤの溝の深さを確認し適切な状態を保つことは、燃費の悪化を防ぎ、環境への影響を減らすことが大切です。
初心者でもできる車検前のタイヤ溝の測り方

上述したようにタイヤの溝は、運転の安全性や法律面も考慮して車検前に一度チェックすることが望ましいです。
しかし、はじめて車検を受ける方はタイヤ溝の測り方をよく知らないかもしれません。
ここでは、タイヤ溝の深さを一目でチェックする方法や正確に測る方法、5円玉を使ったタイヤの溝の測り方などを説明します。
溝の深さを一目でチェックする方法
タイヤ溝の深さを一目でチェックするには「スリップサイン」を目安にします。
タイヤ溝が1.6mm以下になるとスリップサインが出現するので、ひとつでもあらわれた場合は車検には通りません。
また、降雪地帯では冬用タイヤであるスタッドレスタイヤの着用が必要ですが、スリップサインの代わりにプラットホームでタイヤ溝の深さを確認できます。
スリップサインで一目でわかる!
スリップサインとは、タイヤの残り溝が1.6mm以下になると出現するサインです。
タイヤの側面には4〜9個の「△」マークがついており、△マークの延長線上にある溝の底にスリップサインがつけられています。
新品のタイヤは溝の深さが約8mmなので、スリップサインが出た段階で摩擦によりすり減っている状態です。
ひとつでもスリップサインがあらわれると車検には通らないので、事前に確認するようにしましょう。
スタッドレスタイヤはプラットフォームホームを確認
降雪地域や積雪・凍結道路では夏用タイヤではスリップの危険性があることから、冬用タイヤであるスタッドレスタイヤの着用が必須です。
スタッドレスタイヤはトレッド面に細かな切込みが入っており、ハンドルが取られやすい悪路においても走行しやすいのが特徴です。
スタッドレスタイヤでは夏用タイヤのスリップサイン以外にも、タイヤ側面に記載されているプラットフォームホームで残り溝の深さを確認できます。
プラットフォームホームは残り溝が50%以下になったときにあらわれ、冬用タイヤとして雪道では性能が発揮できないことを示します。
スタッドレスタイヤの使用期限の目安はおおよそ新品購入時から3〜4年で、夏用タイヤと同様に定期的にタイヤの状態を確認するようにしましょう。
正確に測る方法
前述した方法では簡単にタイヤの溝をチェックできましたが、正確に測る方法も2つあります。
以下では工具道具を使う方法と専用の器具を使う方法について、詳しく説明します。
工具道具の「ノギス」を使って測る
ノギスとは物の長さを測るのに使用される工具道具で、工具店で簡単に購入できるものです。
主尺目盛りと副尺目盛りを「0」に合わせて、デブスバーという尖った先端部分をタイヤの溝に垂直に置いてスライダーを動かしながら測ります。
副尺目盛りが「0」になっているところで、主尺目盛りで出る数値がタイヤの溝の深さとなります。
タイヤの摩擦を測る専用器具の「タイヤゲージ」を使って測る
タイヤゲージとは、タイヤ取扱店でタイヤの溝の深さを計測するのに使用される専用器具です。
ノギスと同じく主尺目盛りと副尺目盛りの2つがあり、スリップサインの位置を避けて先端部分を溝に垂直に当てることでタイヤ溝の深さを計測できます。
副尺目盛りが0になっているところで、主尺目盛りを読み取るようにしましょう。
5円玉を使ったタイヤの溝の測り方
5円玉と使って、夏タイヤの残り溝を測ることも可能です。以下の図のように、5円玉を溝に差し込み、5円玉の見える部分を確認すれば残り溝を測れます。

5円玉を垂直に差し込んだとき、「五」の文字の三画目の横線が見えたら、溝の深さは約4mmです。これはタイヤの性能が低下し始める目安となるため、交換を考えたほうがよい時期といえます。
さらに「五」の文字がすべて見えると残り溝は約1.6mmで、すぐにタイヤ交換することが必要です。
溝が浅くなると、燃費が悪くなったり環境に悪影響を与えたりすることがあります。安全で快適に走るためにも、定期的にタイヤの状態をチェックし、適切なタイミングで交換しましょう。
スリップサインが出たタイヤを使い続ける3つのリスク

タイヤには「スリップサイン」と呼ばれる摩耗の目印があります。
スリップサインはタイヤの溝が1.6mm以下になるとあらわれ、そのまま走行すると道路交通法違反となるだけでなく、安全性も大きく低下します。
スリップサインが出たタイヤを使い続けると、さまざまなリスクが発生し非常に危険です。
主なリスクは、走行性能の低下やハイドロプレーニング現象の発生、パンクやバーストの危険性が高まることなどです。それぞれのリスクについて詳しい内容を確認しましょう。
1.走行性能に支障が出る
タイヤの溝は、地面をとらえグリップすることで、安定した走行を支える重要な役割があります。そのため、スリップサインが出るほど摩耗すると、グリップ力が低下し、加速やブレーキなどの効きが悪くなります。
とくに、カーブを曲がる際にタイヤが滑りやすくなり、スリップすることで重大な事故のリスクが高まり非常に危険です。
また、摩耗したタイヤは転がり抵抗が増し、燃費が悪化することもあります。走行中の振動や騒音が大きくなることもあり、運転の快適性も損なわれます。
タイヤの性能が低下すると、運転のしやすさや安全性に悪影響を及ぼすため、スリップサインが出たら早めにタイヤ交換しましょう。
2.ハイドロプレーニング現象が発生しやすくなる
タイヤの溝には、雨の日に路面の水を排水し、タイヤがしっかり地面をとらえるようにする働きがあります。しかし、スリップサインが出るほど溝が減ると排水機能が弱まり、雨の日に「ハイドロプレーニング現象」が発生しやすくなります。
ハイドロプレーニング現象とは、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いたような状態になることです。この現象になると、ハンドルやブレーキがほとんど効かなくなり、制御不能に陥る恐れがあります。
とくに高速道路で発生しやすく、重大な事故につながることもあるため、雨の日の安全を確保するためにも、スリップサインが出る前にタイヤを交換することが重要です。
3.パンクやバーストの恐れが高まる
タイヤがすり減ると、ゴムの厚みが減り、内部構造にまで影響が及ぶ恐れがあります。たとえば、過度な摩耗状態のタイヤに小さな石やガラス片が刺さると、急にパンクするリスクがあります。
さらに、長時間の走行や高温の路面の影響でタイヤに大きな負荷がかかると、「バースト」と呼ばれる破裂が起こる危険もあるでしょう。
急なパンクやバーストは、突然タイヤの空気が抜けて車がコントロール不能になり、重大事故につながることもあります。
溝の深さだけでなく、ひび割れや変形がないかも定期的に確認し、早めのタイヤ交換を心がけましょう。
溝以外も確認!車検に落ちやすいタイヤの特徴

タイヤ溝の深さについて解説しましたが、タイヤの溝が1.6mm以上でも車検に落ちることがあります。そこで以下では、車検に合格するための溝以外の項目を解説します。
● タイヤの変形
● 空気圧の低下
また、通常の走行の安全性にも役立つ内容なので、以下の内容をチェックしてください。
ひび割れや傷
車検では、タイヤの劣化状況を確認されます。タイヤはゴムでできているため、使用開始から数年経過するとゴムが硬直して傷やひび割れが生じるためです。
あまり走行していない場合でも、車重によりタイヤに均一に圧力がかかってしまい、ひび割れが起こる場合もあります。
ひび割れや傷が付いたタイヤでは、ハンドリングがうまくきかないことがあり、車検には通りにくくなります。
また、傷やひび割れが深くなると最悪の場合はタイヤが破裂する「バースト」状態に陥ってしまうでしょう。
タイヤの変形
タイヤの変形具合も、車検で確認される項目の1つです。タイヤは劣化や摩擦によるダメージでゆがみやこぶのようなものができ、形状が変形することがあります。
なぜなら、タイヤが変形した状態で走行すると、運転に支障をきたしてしまうからです。
摩擦による変形は均一には起こらず、前後左右で異なります。タイヤが変形したままの場合、道路にしっかり接着せず滑りやすくなります。
この状態では、障害物に接触するなどの事故の原因になりかねません。また、ハンドルやエンジン音に異常が出ることもあるので注意しましょう。
空気圧の低下
車検では、空気圧の状態もチェックされます。
ひび割れ同様、タイヤの空気圧によってもハンドリングがうまくきかなくなり、安全に走行できないので車検に通らない場合も。
適正な空気圧は、タイヤの大きさや車の車種によって異なります。
車の適正な空気圧は運転席側のドアを開けた脇に記載されているので、一度確認してください。
車検費用を安く抑える3つのポイント

車検では、タイヤの溝以外にもさまざまな点検項目があります。車検には数万円から十数万円かかることが多く、できるだけ費用を抑えたいと考える人も多いでしょう。
車検費用には「法定費用」と「整備費用」が含まれており、法定費用はどこで受けても変わりませんが、整備費用は依頼先によって大きく異なります。
費用を抑えるためには、ユーザー車検の利用や複数の業者での見積もり、検査項目を必要最低限するなどの工夫が効果的です。それぞれの方法について詳しく説明します。
1.ユーザー車検を利用する
車検はディーラーや整備工場に依頼するのが一般的ですが、自分で運輸支局に車を持ち込み、検査を受ける「ユーザー車検」を利用することも可能です。
ユーザー車検を利用すれば、法定費用や部品交換代のみで支払いが済み、整備費用や代行手数料がかからないため、ディーラーや整備工場に依頼するより安くなる可能性があります。
ただし、事前に点検や整備を自分で行う必要があり、車の知識がないと難しいのが実情です。ユーザー車検は、車の点検に関する知識があり手間をかけられる人には、もっとも安く済ませる方法としておすすめです。
2.複数の業者に見積もりを依頼する
車検の整備費用は依頼する業者によって異なるため、できるだけ安く抑えたい場合は、複数の業者に見積もりを依頼するのが有効です。
それぞれの業者の車検費用の傾向は、以下のとおりです。
| 業者の種類 | 車検費用の傾向 |
|---|---|
| ディーラー | 費用は比較的高め |
| 整備工場・カー用品店・ガソリンスタンド | 費用は比較的低め |
| 車検専門店 | 割引サービスが豊富 |
見積もりで複数の業者を比較することで、どの業者がコストパフォーマンスがよいのか判断しやすくなります。安さだけでなく、整備の内容やサービスも確認しながら、最適な業者を選ぶようにしましょう。
3.必要最低限の項目だけ検査してもらう
車検では、業者によって追加の整備や部品交換をすすめられることがあります。しかし、すべての検査や部品交換が必要とは限らないため、車検に通過するための、最低限の整備だけを依頼することで費用を抑えられます。
車検に通るために最低限必要な点検項目は決まっており、それ以上の整備は原則任意です。たとえば、「ブレーキパッドの交換」や「オイル交換」などは、まだ使用できる状態なら、車検時に必ず行う必要はありません。
事前に自分で点検し、必要な整備だけを依頼すれば、無駄な出費を防ぐことが可能です。見積もりの際に業者の説明をしっかり聞き、納得できる範囲で整備を依頼することが重要です。
タイヤを長持ちさせるための5つの対策方法

タイヤは消耗品であるため、状態によっては交換が必要です。しかし、何度も交換するとお金もかかるため、長持ちさせたいと思っている方も多いことでしょう。
車種によってタイヤにかかる負担も異なり、摩擦するスピードが速いものもあります。
以下ではタイヤを長持ちさせるための5つの方法を解説するので、日々のメンテナンスの参考にしてみてください。
- ローテーションで摩擦を軽減する
- 適度に空気圧を調整する
- 急発進や急停止を控える
- タイヤを適切な場所に保管する
- ホイールアライメントを調整する
1.ローテーションで摩擦を軽減する
タイヤローテーションは前後左右のタイヤの位置を取り換えて摩擦を抑える方法です。
タイヤの摩擦の速度は車重や装着している位置によっても異なり、エンジンの動力が伝わるタイヤほど摩擦していきます。
たとえば、エンジンと駆動輪がフロント部分に位置するフロント車では前輪が、エンジンが駆動輪の後ろにあるリアドライブ車では後輪が先にすり減ることが多いです。
ローテーションの目安としては、約5,000km走行した時点でタイヤのローテーションを行うようにしましょう。
2.適度に空気圧を調整する
タイヤを長持ちさせるためには、適度に空気圧を調整することが大切です。
タイヤは使用に伴って空気が抜けていくため、調整せずに走行していると本来の性能を維持できなくなります。
空気圧が不足している場合、タイヤ全体が道路に接地せずに偏摩擦や、最悪の場合はタイヤが破裂するバースト状態を起こしてしまいます。
ガソリンスタンドなどでも空気を入れられるので、給油の際に確認して空気が不足する場合は入れるようにしましょう。
3.急発進や急停止を控える
急発進や急停止を控えることも、タイヤを長持ちさせる方法の1つです。
急発進や急停止はタイヤに大きな負担を与えるため、タイヤの寿命を短くする原因になります。
道路には凸凹があるので、通常走行しているだけでも摩擦による影響は受けますが、急発進や急停止はより深くダメージを与えます。
とくに駆動輪はエンジンの動力を道路に伝える役割を担うため、急発進による摩擦のダメージは他のタイヤより大きくなります。
急発進や急停止はタイヤの寿命のみならず、車自体にも大きな負荷がかかるため控えるようにしましょう。
4.タイヤを適切な場所に保管する
タイヤの保管場所と寿命は大きく関係しており、適切な場所に保管することで長持ちさせられます。
不適切な環境でタイヤを長い間、保管していると変形することがあります。
たとえば、タイヤは日光が当たる環境で保管していると紫外線により劣化が進んでしまいます。
保管する際は、日光が直接当たらず雨風を避けられる屋内の風通しがよい環境で、変形しないように空気を半分ほど抜いて立てて保管しましょう。
重ねて置く場合は、ホイールをつけて保管すると変形を防げます。
また、遮光性や防水性を兼ね備えたタイヤカバーを使用することで、結露や埃を防げるのでオススメです。
5.ホイールアライメントを調整する
タイヤを長持ちさせるには、取り付け部分を適正な角度に調整することも大切です。
タイヤは運転の経過に伴って、取り付け部分にズレが生じることがありますが、調整せずに走行すると偏摩擦によって寿命を短くする原因になります。
アライメントとは整列という意味で、ホイールアライメントは車軸を適正な角度に調整することを指します。
安全運転を心がけ、タイヤの空気圧が十分にもかかわらず、偏摩擦が起こっている場合はアライメント(車軸)がズレている可能性が高いです。
アライメントがズレていると偏摩擦によって車がまっすぐに走行しにくくなったり、ハンドルを取られたりする原因にもつながります。
アライメント調整では、キャンバー角・キャスター角・トー角の3種類を調整し、走行性能を高めます。
しかし、過度な調整を行うと、かえってタイヤの寿命を短くする恐れもあるので注意が必要です。
そのため、自力で調整することは控え、時間と費用はかかりますがカー用品店やディーラーに依頼するようにしましょう。
タイヤの溝に関するよくある質問
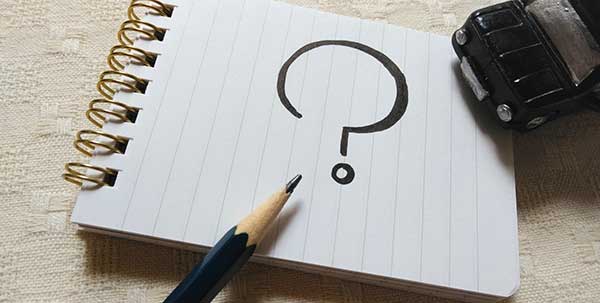
タイヤの溝に関する、以下3つの質問に回答します。
● タイヤの寿命はどのくらい?
● タイヤは1本だけ溝が少なくても4本交換したほうがいい?
タイヤ交換の際に大切な情報も含まれているので、車検やタイヤ交換が近づいている方は、ぜひ参考にしてください。
タイヤの溝が4mmだと車検に通らない?
車検に合格するための最低限のタイヤの溝の深さは1.6mmです。
そのため、4mmの溝があれば車検には問題なく通ります。
しかし、4mmを下回るとタイヤの性能が低下し始めるため、交換を検討し始める時期です。
とくに、雨の日のグリップ力や燃費への影響が大きくなるため、安全性を考えると、タイヤの溝が3~4mm程度になった段階で早めに交換したほうがいいでしょう。
タイヤの溝は車検に通るかどうかだけでなく、快適で安全な走行のためにも定期的にチェックしましょう。
タイヤの寿命はどのくらい?
タイヤの寿命は走行距離や使用環境によって異なりますが、一般的には3~5年です。
走行距離での場合は、3万~5万km が目安とされています。
たとえタイヤの溝が十分に残っていても、ゴムの劣化が進むと性能が落ちるため、適切なタイミングで交換することが重要です。
ひび割れが目立ったり、ゴムが硬くなったりしている場合は、グリップ力が低下し、安全性を損なうため大きな事故につながるリスクもあります。
使用頻度や走行距離が少なくても、長期間使っていないタイヤは劣化するため、製造年数を目安に交換を検討しましょう。
タイヤは1本だけ溝が少なくても4本交換したほうがいい?
タイヤは前後または左右でバランスを取るため、1本だけ交換するよりも、2本または4本セットで交換するのが理想的です。
片方だけ新しいタイヤにすると、左右のバランスが崩れ、走行時の安定性が損なわれる恐れがあります。
たとえば、前輪駆動の車で前輪の片方だけ交換すると、左右のグリップ力が違い、ハンドル操作に影響を与えることもあります。4WD車では、前後のバランスが崩れ、駆動輪の負担が増すことも考えられるでしょう。
タイヤは4本すべてを交換するのが理想ですが、少しでもコストを抑えたい方は、安全性を確保するためにも、前輪2本または後輪2本を交換するのがおすすめです。
タイヤの点検ならタイヤワールド館ベストがおすすめ

車検に通るためには、最低でもタイヤの溝は1.6mm以上残っていないといけません。ただし、安全な走行のためには、3〜4mm以上の溝が残っている状態が理想的です。
車検に通るタイヤの溝の深さはあくまで最低限のラインであり、安全で快適な運転のためには、タイヤの溝が4mm以下になった時点で交換を検討しましょう。
タイヤワールド館ベストは全国に約4,000の提携店舗があり、タイヤに関する相談を随時受け付けております。
タイヤの溝や車検などをはじめ、タイヤに関するさまざまなことにお悩みの方は、タイヤワールド館ベストの提携店舗を検索して、ぜひお気軽にご相談ください。

2022年6月からベストライターチームとして本格始動!
タイヤやホイール等車に関するあらゆる悩みを解消できたり、
購入する時のポイントなど
足回りを取り扱うプロとして執筆していきます!
公式InstagramやTwitterも更新しているので是非
そちらもご覧ください!